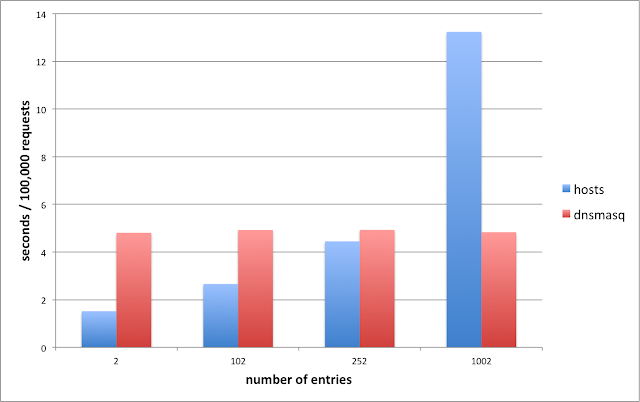Open Network Lab で開催された
Growth Hacker Andrew Johns Meetup に参加して来ました。Facebook、Quoraのユーザー獲得チームで働いていた方です。
講演内容
講演の内容は3つでした。
1. ユーザー獲得は家計と同じ
- 数パーセントの違いが複利で効いて、1年後には大きな違いを産む
- 収入(ユーザー)を増やすことと、負債(技術的負債)を減らすことのどちらも重要
- 一ヶ月で100%の成長が一回きりと、毎週3%の成長が1年間では後者のほうが効果を生む
- 毎週1%の成長で年1.7倍、毎週3%だと1年で5倍の成長になる
2. 成長は個人だけでやることではなく、会社の変革が必要
- 会社の文化が成長を求めるよう、文化を変える
- 社内で積極的に情報発信し、チームを変え、会社のDNAを変える
- "Growth Hack"の対象には会社自身も含まれる
3. シンプルさが大事
- 機能を追加すると複雑さが増し、ユーザーは減少する(特に資金を得た後が危ない)
- ユーザーを追うメトリックも単純なものを選ぶ
- ゴールやチームのミッションもシンプルで共有しやすいものにする
そして大事なこととして「ダメなサイトを持続的に成長させることは不可能。プロダクトが優れていることは絶対条件。」が示されました。良いプロダクトの目安として、例えば1000人の新規登録ユーザーのうち2~3割が翌月も使い続けているとすると、そこそこ良い線だということです。
話の途中、いくつかの事例が示されました。
KPIとしては K + sqrt(abc) を使う。変数はそれぞれ
- K: バイラルでの成長
- a: プロダクト数の増加
- b: プロダクトあたりのトラフィック
- c: 売上のコンバージョン率
例えばamazonでは、aは極めて大きく、bも「プロダクトごとにpermalinkがあり、検索エンジンから流入するし、口コミでリンクを貼れる」などと工夫しています。Qiitaのようなサイトではaは記事数、bは記事あたりのトラフィック、cをサインアップする人の割合と読み替えると良いでしょう。
そして単純なKPIを決定したら、それぞれの部分、K, a, b, cごとにチームを組み、ミッションを割り当てるのが重要とのことです。例えばaを増やすのに専念する渉外チーム、bに専念するエンジニアチーム、cに専念するデザイナーチームという感じです。
この中でKを増やそうとするのは危険だそうです。というのも、口コミはコントロール出来ないし、企業が展開すると「押し付け」のようになってしまうからだそうです。
劇的な改善ができた例として、Twitterのサインアップページの例がありました。
Twitterでは、ユーザーが増加するに従いユーザー名の衝突が起きやすくなりました。そこで、サインアップページで氏名を入力すると、自動的に衝突しないユーザー名を提案し、フォームに自動入力する機能をつけました。そうすると、毎日6万人の新規登録が増えたそうです。
企業のDNAが重要な例として、MySpaceのトップページが挙げられました。
MySpaceでは収益を重視して、トップページに広告を掲載しました。すると新規登録が減少したというのです。逆にFacebookはユーザー増加が最重要ということで、トップページは新規登録に必要な情報に絞った結果、ユーザー数が増加するようになったとか。
実験を簡単に、多数できるようにする環境づくりも重要だそうです。
Quoraでは新しいことをすぐ実験、数値解析ができるプラットフォームに投資し、200以上の実験を行なってくることができたと示されました。とにかく実験しないと、例えば70個ぐらいのアイデアのうち多少なりともうまく行ったのは15個、大成功したのは3個程度という打率で、やってみないとわからないことも多そうです。
感想
今までのKPIはDAU, ARPUなど「ストック」に注目するものが多かったところ、「フロー」に着目して成長を定量化するという視点が新鮮でした。いかにユーザーが登録までに遭遇する障害を取り除くかというところに着目するとこれだけ新規登録が増えるということは、変なフォームで諦めてしまう人も多いのかなと思いました。
最近どのようなKPIを取ればプロダクトの状態がわかるかというのが話題になっていますが、この「フロー」をよく見るいうのはひとつの答えだと思いました。